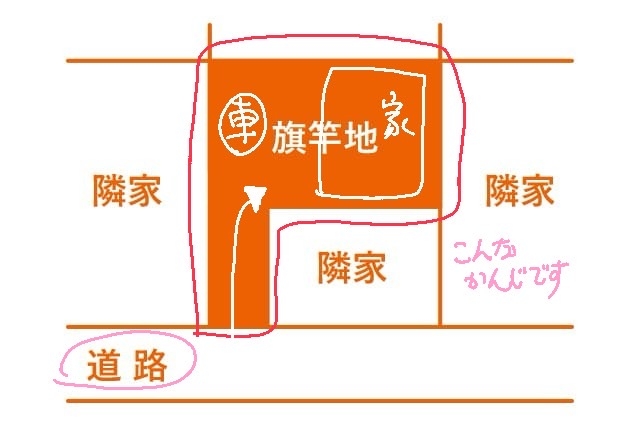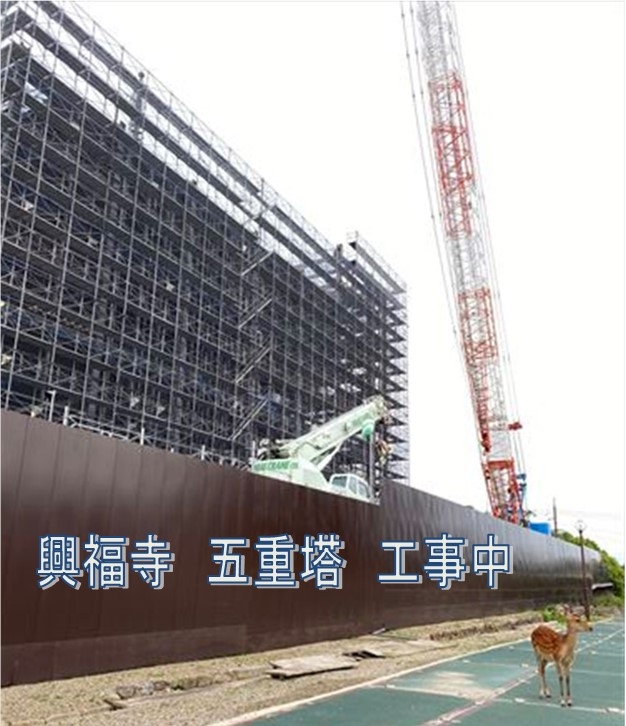耐震診断は、新しい家でもみたほうがいい理由
こんにちは!
プラント3にシュモクザメが魚コーナーで並んでいて、
思わず写真撮ってしまった、ミーハーな小澤です^^;
んーーーーこれは美味しいのだろうか。。。
ハンマーヘッド!^^
毎年性能向上リノベの会の耐震診断 耐震補強工事等オンライン勉強会に参加しています
毎年内容的には基本変わらないのですが
非常に大事なことなので
基本に立ち返るために必ず受講しています
では一体何が重要か?となるのですが...
地震に対する強度不足な家 つまりめちゃくちゃ古い家は
耐震診断や耐震補強工事に補助金を出しますよ
と国の制度で住宅の耐震化率を上げる政策がとられています
しかしここには大きな落とし穴があり非常に問題が隠れています
小澤工務店が立てている家は常に最新の法律に基づいて必要以上の工事をして補強を施しながら建てています
たとえば必要以上に丈夫にすることなどでしょうか。。。
また確認申請の時に必要でない構造の確認チェックなども全て行っており
添付も必要は無いのですがそれも計算しています
日本全国の木造住宅の建設業者がそのようにしていればいいのですが
実際はまったく違います
現在日本全体の木造住宅で約8割が大地震に対してもう対応済み、
と一部変な情報がまかりとおっていますが
実はとんでもなく大きな間違い いや勘違いです
耐震診断や補強工事の補助金の対象は、昭和56年以前の木造住宅になっていますが...
では昭和56年以降の住宅であれば何も問題ないのか?
答えはノーです
端的にわかりやすくお伝えしておくならば
今年の1月1日に起こった能登自信での被害がまさにそれを表しています
実際私も珠洲市へボランティアに行って目の当たりにしてきましたが
本当に古い家はもちろんのこと
比較的新しい家を何らかの被害が起きている状況なども見受けられました
仮に今なんともなくても実は深刻なダメージをかかえたままの住宅もひじょうに多く存在します
詳しくはまた後日書きますが
耐震診断に補助金が出ない比較的新しい住宅も実はちゃんと設計されていない
そんな木造住宅がかなり存在すると言う事実。。。
これを知ると一般の人はものすごく不安になると思います
地震が来ないとわからないです実際
もしもリフォームをおこなうときは
できる範囲で少しでも補強をおこないましょう^^